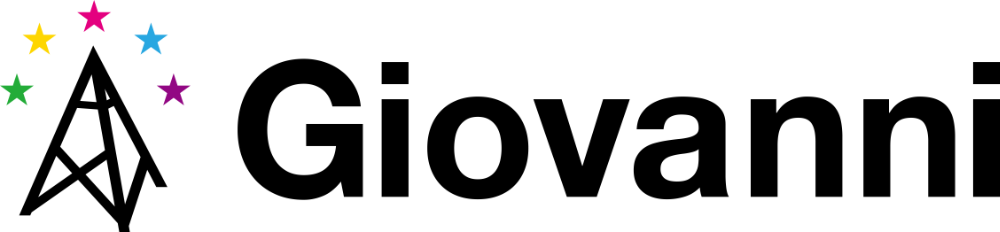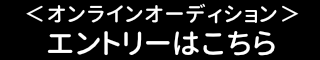ジョバンニが仕掛ける「逆転の発想」
音楽事務所「ジョバンニ」をご存知でしょうか。一見すると、数ある音楽プロダクションの一つかもしれません。しかし、公式サイトに掲載されている情報を少し深く見ていくと、その運営方針が非常にユニークであり、強い情熱に基づいていることが伝わってきます。
この記事は、外部のライターという視点から、ジョバンニのその特徴的な取り組みを分析するものです。
結論から伝えると、ジョバンニを理解する鍵は、彼らがエンターテインメント業界の常識に挑戦する、「本気」に基づいた独自のシステムを構築している点にあります。
このシステムを象徴しているのが、彼らが掲げる「武道館のステージを約束する」という宣言です。
音楽業界において、武道館は一つの大きな目標とされています。通常、アーティストは小さなライブハウスから活動を始め、地道に実績を積み、ファンを増やした結果として、いつか立てるかもしれない場所。それが一般的な「常識」です。
しかし、ジョバンニはここの「逆転の発想」を用いています。彼らは「小さなライブ」→「実績」→「武道館」というプロセスではなく、「最初に武道館を約束する」→「“本気”の覚醒」→「全力の行動」というプロセスを採用しているのです。
なぜでしょうか。ジョバンニの理念は「“何者でもない誰か”が、武道館という大舞台を目指し、夢を実現できる世界を創ること」にあります。代表の立石憲司氏は、人が「いつか武道館に立てたら」と夢見ているうちは本気になれないが、「絶対にここに立つ」と決めた瞬間、人は変わると信じているのです。
そのため、ジョバンニはまず武道館の日程を押さえてしまいます。実際に、2024年3月6日の武道館公演を実現させた実績を持ち、直近では2026年1月14日(水)の「ジョバンニ 44 フェス in日本武道館」の開催を決定しています。2027年の武道館公演も開催を予定しているようです。
これは単なる目標設定以上の意味を持っているように思えます。
この「武道館のステージを先に用意する」という宣言は、ある種の「フィルター」として機能しているのではないでしょうか。
例えば、「そんなのは無理だ」と考える人や、「大きなステージに憧れる」という程度の気持ちの人にとって、2026年1月14日という具体的な期限は、夢ではなく「プレッシャー」として感じられるかもしれません。
結果として、この宣言に引き寄せられて応募してくるのは、「自分にはここしか残されていない」と考える人、あるいは「自分の可能性を本気で試したい」と望む、覚悟の決まった人々に絞られるのではないでしょうか。
つまり、ジョバンニの「武道館の約束」は、単なるPR戦略ではなく、オーディションの第一段階として機能する、巧みな選別メカニズムなのかもしれません。
「本気」の育成環境:報酬保証と、3ヶ月の更新条件
では、その最初の「フィルター」を通過した先には、どのような環境が待っているのでしょうか。
ジョバンニは、本気の人のために、二つの特徴的な環境を用意しています。一つは、手厚い「支援」。もう一つは、明確な「条件」です。
まず、手厚い「支援」から見ていきましょう。
ジョバンニは、オーディションを経て採用された研修生に対し、最初の3ヶ月間、「月30万円(税込)の報酬保証」を提供しています。
月30万円。これは、音楽事務所、特に新人や研修生に対して、これほどの金額を「保証」するというのは、業界内でも特に手厚い、異例のサポート体制と言えます。多くの事務所がレッスン料を徴収したり、無給でアーティストを活動させたりすることと比較すると、その違いは明らかです。
この「支援」の背景には、代表・立石氏の強烈な原体験があります。彼は自身のメッセージで、20代の頃、音楽活動に集中したくてもアルバイトに時間を奪われた苦悩を吐露し、「もしあの時、あの若い時間のすべてを音楽活動に注げていたらどうなっていただろうか?」と自問しています。
月30万円の保証は、彼のその「問い」に対する「答え」であり、「最初から夢に全集中できる環境をつくる」という決意の表れなのです。
ただし、重要なのは、これが単なる「給料」ではないという点です。立石氏は、この報酬が先輩アーティストやスタッフが稼いだお金を「次世代の挑戦者への先行投資」として差し出しているものだと明言しています。これは「応援のバトン」であり、受け取る側には相応の「責任と覚悟」が求められる、と述べています。
だからこそ彼は、「『報酬がもらえるから』くらいの興味本位での参加は絶対にしないでほしい」と、公式サイトで強く呼びかけているのです。
なぜ、そこまで強く呼びかけるのでしょうか。それは、この手厚い「支援」が、明確な「条件」と表裏一体だからです。
ジョバンニの所属アーティストは、研修生を含め、「3ヶ月ごとの業務委託契約」で活動します。そして、その契約が更新される条件は、非常にシンプルです。
- 3ヶ月間の売上目標の達成
- 契約違反がないこと
ここに、ジョバンニというシステムの「本気」が凝縮されています。
ジョバンニは、アーティストを「庇護すべき対象」としてだけではなく、「対等なビジネスパートナー」として扱っているように見えます。
このシステムは、非常に透明性が高いと言えるでしょう。
月30万円という「先行投資」は、挑戦者が生活の心配をせず、100%「本気」で活動にコミットするための「サポート」です。
同時に、「3ヶ月の売上目標」は、挑戦者が結果を出せなければ契約が更新されないという「条件」でもあります。
この手厚い支援と明確な条件の組み合わせこそが、ジョバンニが「本気の人だけが続けられる環境」と自負する理由でしょう。この環境下に身を置けば、人は「本気」にならざるを得ないのかもしれません。
ジョバンニの“特異な活動”:路上、カフェ、配信が織りなす「本気」の現場
では、アーティストたちは、その「3ヶ月の売上目標」という条件をクリアするために、具体的に何を求められるのでしょうか。
活動内容のページで説明されているのは、一般的な音楽事務所がイメージする「レッスン」や「レコーディング」といった、スタジオ内での活動とは少し異なる、「現場」中心の活動です。
- 路上ライブ (ストリート活動)
ジョバンニは、路上でのリアルなパフォーマンスを重視します。ですが、それは「いつか誰かが見つけてくれるかも」という活動ではありません。「『誰も立ち止まってくれない』から始まる」と明記されています。これは、ゼロから「自分を本気で応援してくれる人」に出会い、ファンを「育てる」ための、実践的な活動です。 - ライブバー 「UP DRAFT」
所属アーティストは、テーマ型カフェのキャストとしても活動します。これは単なるアルバイトではなく、「ファンを拡大させていく場」であり、「個性や表現力を“人と接する現場”で磨ける」場として、明確に位置づけられています。 - ライバー (配信者)
TikTok LIVE、17LIVEなどでのライブ配信も、重要な活動です。「投げ銭」やファンとの交流で「収益を得る」新しいスタイルであり、「届ける力」「魅せる力」を育てる場とされています。 - ライブ活動(チケットの手売り)
もちろん、ライブハウスやTokyo Dome City Hall、豊洲PITといった大きなイベント会場での主催イベントにも出演します。ですが、重要なのは「ライブに出るだけ」ではない点です。「チケット販売の手売りや集客も『自分の力で届ける』重要な役割」として、アーティスト自身に課せられています。
これらの活動の共通点は何でしょうか。それは、すべての活動が「市場(=ファン)」に直結し、かつ「収益(=売上)」に直結していることです。
伝統的な事務所がアーティストを「製品」のように扱い、市場から隔離された「レッスン室」という環境で完成度を高めてから「発売」する傾向があるのに対し、ジョバンニは異なるアプローチをとっています。
彼らはアーティストを「ビジネスパートナー」として扱い、活動初日から市場(路上、カフェ、配信)に出します。彼らにとって、「育成」と「ビジネス」は同時に進行するものなのです。
このシステムが机上の空論でないことは、所属アーティストたちのブログからも伝わってきます。
「4年2組」のLeo氏は、「1人でも路上ライブをやり続ける意味」について深く内省し、「あんなに一人で路上をやるのが嫌だった自分」がなぜ変われたかを綴っています。
「-SETSUNA-」の竹之内理沙氏は、水戸への遠征を続け、「一人で路上をするようになり、毎月通ううちに」応援者が増え、それが「楽しみへと変わっていきました」と報告しています。
ジョバンニの「特異な活動」は、単なる訓練ではないようです。それは、アーティスト自身が「どうすればゼロからファンを獲得し、収益を上げ、生き残ることができるか」を、身をもって学ぶための実践的なプログラムと言えるでしょう。
「誰も立ち止まってくれない」路上からスタートした経験は、アーティストを強くするのかもしれません。彼らは、用意されたステージで歌うだけの「タレント」ではなく、自らステージを創り出す「アーティスト」として鍛えられていくのです。
「本気」は伝染する:アーティストから社長、スタッフまで貫かれる覚悟
ジョバンニというシステムがなぜ機能しているのか。その最後のピースは、「人」にあるようです。
この「本気」のシステムは、アーティストだけに「本気」を求めるものではありません。それは、社長からスタッフに至るまで、組織全体を貫く「覚悟」によって支えられています。
まず、代表・立石憲司氏の「本気」です。
彼のメッセージは、単なる経営者の挨拶ではありません。それは「本気」の挑戦者を探すための、情熱的な呼びかけです。
彼は、ジョバンニが求める基準を「トップアーティスト」「トップアイドル」であり、紅白やアリーナツアーだと明確に定義します。生半可な成功には興味がないと公言しています。
そして、彼は挑戦者に対し、甘えのある関係を許しません。「『何をしてくれるか』ではなく、『自分がこの環境をどう活かすか』を考え、本気で全エネルギーを注ぐ決意ができる人」だけを求めているのです。
彼は「環境は提供する。でも、そこから這い上がるのは自分自身です」と述べる一方で、「無名のあなたに、先に大舞台を与える」「僕たちが信じる」と、挑戦者以上の「覚悟」をもって共に戦うことを宣言しています。
このトップの「本気」が、組織にまで浸透していることを示す情報が、スタッフの「求人情報」です。
ジョバンニの「本気」を真に理解するためには、この求人情報を読むことが役立ちます。なぜなら、ここにはアーティストとスタッフが「本気」によって連携する、組織構造が示されているからです。
彼らが募集しているのは、単なる「事務員」や「アシスタント」ではありません。
例えば、「アーティストマネージャー」の募集要項。業務内容には、「スケジュール調整」といった一般的な業務に混じって、決定的な一文が記載されています。
それは、「アーティスト予算達成・管理(インセンティブあり)」そして「CD・グッズの売上達成サポート」です。
次に、「ライブバー店長」の募集要項。ここでも、単なる店舗運営能力が求められているのではありません。その目標は「コンカフェから武道館アイドルを生み出し、世の中に『誰しも可能性がある』というメッセージを伝えられる店舗を作りたい」という、非常に高いものです。
この「本気の連鎖」が、ジョバンニというシステムの仕組みです。
そこには、「アーティストは才能だけ考えていればいい」「スタッフは時間通りに働けばいい」という、従来の業界に見られたような関係性とは異なる、厳しさがあります。
社長の「本気」が、アーティストの「本気」を、そしてスタッフの「本気」を呼び起こし、互いを高め合う。この「本気の全面的な連携」こそが、ジョバンニの強さの源泉なのでしょう。
結論:ジョバンニは、音楽業界における「本気」の試金石
ここまで、音楽事務所「ジョバンニ」が、なぜ「本気」という言葉を追求するのかを、彼らが公開する情報を基に分析してきました。
その答えは、彼らが「本気」という一つの概念を、合理的に追求する「システム」を構築しているからだ、という結論に至りました。
この「本気」のシステムは、以下の要素で構成されています。
- 「ヤバイ」目標設定(逆転の発想)
「いつか」という曖昧な夢を排除し、「2026年1月14日」という具体的な武道館の「約束」を先に提示します。これにより、覚悟のない人をふるい落とし、本気の挑戦者だけを引き寄せます。 - 「ヤバイ」投資と選別(VCモデル)
「月30万円の報酬保証」という手厚い「先行投資」で、挑戦者を生活の不安から解放します。同時に、「3ヶ月の売上目標達成」というビジネスの結果で、明確に「選別」します。 - 「ヤバイ」育成(起業家モデル)
レッスン室ではなく、「路上」「カフェ」「配信」という「市場の最前線」に立たせます。「誰も立ち止まってくれない」場所から、自力でファンと収益を生み出す力を鍛え上げます。 - 「ヤバイ」組織(本気の連鎖)
アーティストの「売上目標」と、スタッフの「予算達成」を連動させます。組織全体が「結果」に対して「本気」にならざるを得ない、強固なシステムを築いています。
ジョバンニは、もはや従来の「音楽事務所」というカテゴリーには収まらない、エンターテインメント業界に「ビジネスのリアリズム」を持ち込んだ、ユニークな存在と言えるでしょう。
このシステムは、夢を追うことの「本気」を測る試金石のようです。「自分を試したい」という漠然とした憧れしか持たない人にとって、ここは厳しすぎる環境かもしれません。「何をしてくれるか」と期待する人は、3ヶ月も経たずに去ることになる可能性もあります。
しかし、「何者でもない」自分を諦めきれず、最後のチャンスとして全エネルギーを注ぐ覚悟を決めた人間にとって、これほど「本気」になれる環境はないのかもしれません。
なぜなら、ジョバンニは「本気」で挑戦する人間を、「本気」で信じ、「本気」で投資し、「本気」で戦うことを約束しているからです。
ジョバンニは、音楽業界の「夢」という曖昧な言葉を解体し、「本気」という名の「結果」を求める、注視すべき存在と言えるでしょう。